
朗読付き短編小説 『鬼胎児』 (レグルス)
短編小説を書きました。西峰憂さんの朗読付きです。どうぞ。
※Google chromeでは音声プレイヤーがうまく表示されない場合がございますのでご注意ください。
『鬼胎児』
1.
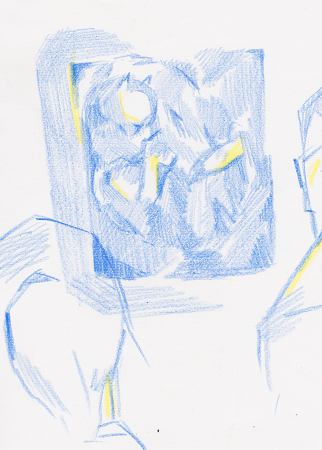
「鬼って何ですか」
頭に角が生えていて、虎柄のパンツを履いていて、と医者が説明するものだから、私は手をひらひらさせて話を止めた。鬼の概要は知っている。
「鬼を妊娠したって、どういう意味なんですか」
中年の医者は面倒くさそうに答える。
「そのままの意味ですよ。あなたのお腹の中には鬼の赤ちゃんがいます」
私は今まで男性とお付き合いをしたことがなかった。それなのに、いきなり妊娠していると告げられても反応に困る。それも普通の子供ではなく、鬼だ。もちろん鬼と愛を育んだ覚えもない。鬼って何ですか、とまた口に出しそうになる。
お腹の中のエコー写真を見せて貰った。確かに、黒い影が私の体内に写っている。普通の胎児に見えなくもないが、大きな頭に、不格好な二本の角のようなものがくっついていた。家に写真を持って帰ってからも、しばらくその不思議な形の頭を眺めていた。
医者は、中絶するなら早くした方がいいと言っていた。人工妊娠中絶は、妊娠12週目を越えると手続きがややこしくなるそうだ。妊娠したばかりの人間に中絶の話をする医者はどうかと思う。「最近よくあるんですよ」と言われたが、こんなことが頻繁に起きていたら堪らない。
六畳の部屋で仰向けになり天井を見つめた。とても親には言えないな、と考える。大学を卒業した娘が、就職できずにいるどころか妊娠したと知ったら、どんな顔をするだろう。きっとまた私を蔑むような目で見るに違いない。「鬼の仕業です」と正直に話せば許してもらえるだろうか。
お腹の中で、何かが動いたような気がした。得体の知れないものが自分の中で蠢いているということを、改めて意識する。エイリアンの出てくる映画を思い出してしまい、鳥肌が立った。お腹を突き破って出てくるようなことは勘弁してほしい。やはり鬼が大きくなる前に、堕胎するべきなのだろう。
2.
私にはお金がない。大学を卒業してからは仕送りも減らされた。結果の出ない就職活動のかたわら、アルバイトをして暮らしている。バイト先では黙々とお弁当を作っていた。
お弁当のおかずを詰めていると、パートのおばさん達の声がよく聞こえてくる。店長の悪口が主な話題のようだった。うるさく喋りながらも、彼女たちは手を止めずに仕事をこなしており、その姿に感心する。私は黙って作業しているが、おばさん達よりも要領が悪い。最初のうちはおばさん達が話しかけてくることもあったが、私が無愛想で気の利いたことも言えない、つまらない人間だと気付くと、次第に私の周りには誰も近づかなくなっていた。
店長に私の出勤日数を増やしてほしいと伝えた。私は仕事ができる方ではないため、あまり良い顔はされなかったが、渋々了承を貰えた。ちょうどパートのおばさんが一人辞めるので、シフトに空きが出るらしい。なぜ出勤日数を増やしたいのか聞かれたが、さすがに中絶するためにお金が必要だとは言えなかった。
アルバイトの日数を増やしただけで解決できる問題なのかは疑問だった。今の時給では、鬼が生まれる方が先になってしまうかもしれない。まだお腹の大きさに変化はないが、これから自分の身体はどうなるのか、不安が残る。
そういえば、心配することを俗に「鬼胎を抱く」と言うらしい。今の私は文字通り、鬼胎を抱いているわけだ。くだらないことを考えていても、答えは見えてこない。
3.
アルバイトで失敗をして店長に怒られた。注意力が散漫になっていたのかもしれない。給料の前借りをできないか相談しようと思っていたのだが、これではとても言い出せそうにない。パートのおばさんの冷ややかな視線を感じる。俯いている私の背中に、ひそひそとした声が突き刺さった。
自宅に帰ってから、携帯電話に着信があったことに気付く。留守番電話には父の不機嫌そうな声が録音されていた。メッセージを要約すると、早く仕事を見つけろ、せっかく大学にまで行かせたのだから恥をかかせるな、という内容だった。有名企業への就職が決まっている妹のことを引き合いに出し、いかに私が駄目な人間なのかを父は説いていた。
いつもそうだった。妹は聡明で人当たりもよく周囲から愛されている。彼女と違って私は誰かと笑い合ったりできず、人の目を見て話すことができない。必然的に家族や親戚は妹を可愛がり、私には何の期待もしなくなった。
色々な感情がミルフィーユのように積み重なって、うまく気持ちの制御ができずにいた。崩れ落ちるようにしてベッドに倒れ込む。狭い部屋に自分のすすり泣く声だけが聞こえる。ベッドのシーツに涙が染み込んでいき、その部分だけが熱い。私は、この広い世界でひとりぼっちになってしまったのではないか、誰も私の味方なんていないんじゃないかと、とても大人とは思えない幼稚な考えさえ浮かんでくる。
むせび泣いた余韻を残しながらまどろんでいると、身体の奥にゆっくりとした鼓動を感じた。心臓とは別の場所から響いてくる。鬼だ、と気付くのに時間はかからなかった。お腹の中にいる鬼の鼓動が、私にまで伝わってきている。
エコー写真で見た、角を生やした鬼の姿を思い出す。心臓の鼓動だろうか。緩やかな一定のリズムは心地良く、私は眠りに落ちるまで、その鼓動に身を任せていた。まるで、子供の背中をポンポンと優しく叩いて寝かしつける母親のようだ。これでは逆じゃないか、と頭の片隅で思いながら、意識は深く沈んでいった。
4.

「あんた、最近頑張ってるねえ」
肩を震わせて振り返ると、声をかけてきたパートのおばさんは、そんなに驚かなくてもいいのに、と笑った。人と話す心の準備ができていないと、上手く会話できない。不意に声をかけられるのは苦手だ。
「ミスも少なくなったし、私らよりも仕事が早くなったって、店長がびっくりしてたよ」
そのおかげで私らのお喋りがよく注意されるようになったけど。そう言いながらも彼女は愉快そうにしている。特に自覚はなかったのだが、確かに最近は店長からあまり怒られていない。
「こんなに頑張って、何か欲しいものでもあるわけ?」
「欲しいもの?」
「そのためにお金が必要なんじゃないの?」
彼女の言葉を聞いてはっとする。何故お金が必要なのか、思い出すのには時間を要した。理由を見失っていたようだ。
胎内にいる鬼の存在は、それほど悪いものではなかった。鬼は、私のことを何も否定しない。余計な干渉もしない。ただお腹の中で熱を持ちながら、心臓の鼓動や胎内の壁を蹴る振動を伝えるだけだった。周囲に心を許せる人がいない私にとって、鬼の存在は大きくなりつつあった。
幽霊が出てきそうな暗い夜道を歩いているときも、鬼と一緒なら心強かった。実態のない幽霊なんて鬼に比べたら可愛いものだ。そう思うことができた。こっちなんて体の中に鬼がいるのだ、と。
鬼との共存に慣れ、精神的にも安定した日々を送っていた。妊娠したということをパートのおばさんに打ち明けてしまったのも、誰かにこの喜びを伝えたかったからなのかもしれない。
翌日から、当たり前のようにパートのおばさん達から話しかけられるようになった。独自のネットワークによって、私の妊娠はおばさん達の間に知れ渡った。話しかけられる度に私はぎこちなく対応している。ただ、嫌な気持ちはしなかった。ときには笑顔を交えながらおばさん達と話す私の様子を見て、ネットワークから一人だけ外れている店長は、不思議そうな顔をしていた。
ある日、パートのおばさんから絵本を貰った。まだ生まれてもいないのに気が早い。家に帰ってから確認すると、桃から生まれた男の子が鬼退治をする、有名な内容の絵本だった。ぱらぱらとページをめくると、男の子やお供の動物によって、鬼がやっつけられている場面が描かれていた。鬼に読み聞かせるのはあまりよくなさそうだ、と苦笑したあとで、自分が鬼を産もうとしていることに、やっと思い至る。
アルバイト先からの帰り道、建物が取り壊された空き地の隅に、目立たないように花が咲いていた。黄色くて小さい花は、まだ少し肌寒い気温の中でも、四方に花びらを開いている。花に近づいて甘い匂いをかぐと、まるでその匂いを感じて喜ぶかのように、お腹の中から鼓動が伝わってきた。この子にも綺麗な花を見せてあげたい。気付くと自然にそう考えている。もうすぐ、妊娠してから12週間が経つ。
5.
男が訪ねてきたのは突然だった。男はとある施設の研究員だと名乗り、医者に紹介されてやってきたと話した。そういえば、数日前の検診で鬼を産む意思を医者に伝えていた。
中絶する際の一切の費用を負担する代わりに、鬼を施設に提供してほしい。男の話は単純なものだった。「施設」というのが一体何の施設なのかは説明されなかったが、大体は察しがつく。私はもちろんその提案を断った。
「本気で産もうと思っているのですか」
男は無表情で言葉を話した。質問にうなずく。
「あなたが妊娠しているのは鬼ですよ。ご存じですよね」
「知ってます」
「得体の知れない化け物を、産んで、育てる気なのですか」
そんな風に言わないで下さい。そう口にしながら、不意に不安が込み上げてくるのを感じた。鬼を産み、育てる。
「見たところ、あなたは裕福とは言い難い。人間の子供でさえ育てることは難しいでしょう。それなのに、どうやって孕んだかも分からない鬼の子供を育てるなんて、無理だと思いませんか」
正論だった。男の話は長時間続き、最初は反論していた私も、次第に口数が少なくなっていった。男が口を開くたびに、自分がどれだけ物事を深く考えず、短絡的な行動をしようとしていたかを思い知らされた。男は怒鳴ったりせずに論理的に話を進め、最終的には施設の管轄の病院で中絶手術をすることになっていた。そのときには私も、鬼を産もうなどという考えは、一時の気の迷いだったと思うことができた。
男が帰って一人になったあと、晩ご飯を食べ、お風呂に入り、ベッドに横になって目を閉じたところで、急にやりきれない気持ちが込み上げてきて、暗い部屋でうめき声をあげた。それからの数日間は、なるべく何も考えないようにして過ごした。
6.
これは後から聞いた話なので、詳細は分からない。
帝王切開の手術をすることになり、私は早い段階から麻酔で眠っていた。手術には医者の他に、あの施設の男も立ち会っていたそうだ。私のお腹は切り開かれ、鬼の胎児は取り上げられた。そのときに鬼がどのような姿をしていたのか、今となっては知る由もない。
手術室が真っ赤に染まったのは、私のお腹を縫合し終えた直後だったという。叫び声が聞こえて医者が振り向くと、施設の男の首筋に鬼がぶら下がっていた。鬼の体は血に濡れ、床には血だまりができていたそうだ。噛みつかれた男は重症を負ったが、一命は取り留めたらしい。だが阿鼻叫喚の巷と化した手術室の中で、いつの間にか鬼の姿は消えていた。
7.
お腹の傷も目立たなくなった頃、就職した私は鬼のことなどほとんど忘れていた。仕事もある程度順調で、少ないながら友達もでき、親からとやかく言われることも少なくなっていた。
ある朝、会社に行こうとして家を出ると、足元に小さな花束が落ちていた。何本かで束ねられている黄色い花は、誰かの仕業で置かれたように見える。緩い風に、小指ほどの花弁がそよいでいた。拾い上げると、かすかな甘い匂いが鼻腔に広がった。ああ、と溜め息を漏らすと、私はその場でしばらく立ち止まっていた。頭の中で色々なことが思い起こされ、動くことができなかった。
今でも、その花の咲く季節になると、一緒に過ごした胎児のことを思い出し、そして謝罪する。

終

存在しない


